8k 産業革命期の日本経済
このページは、当時の日本の経済状況について、です。産業革命期に突入していた日本経済の状況について、また、産業革命の象徴とも言える鉄道の日本での発達史に関する参考図書も挙げました。
このページの内容
産業革命期だった日本の経済
石井寛治 『日本の産業革命-日清・日露戦争から考える』
朝日選書 1997 (再刊 講談社学術文庫 2012)
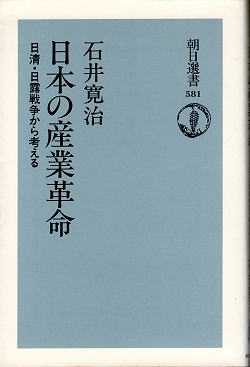
本書の目的について、著者は「序章」の中で、「歴史研究の細分化と分散化を克服して、歴史の全体像をあらためて組み立てる」こと、そのさい「産業革命の真っ最中に日本が東アジアにおいて経験した二つの」「戦争と産業革命の関係を考える」ことであるとしています。
一口で言えば、1873(明治6)年の政変以後、第1次世界大戦が起った1914(大正3)年までの約40年の期間についての、日本経済史の概説書です。分かりやすい記述で、日清戦争の研究者には必読書の1冊であるように思います。
なお、本書は、現在は講談社学術文庫から再刊されています。
本書は、本ウェブサイト中、下記のページで引用等を行っています。
大江志乃夫 『日本の産業革命 (日本歴史叢書)』
岩波書店 1968
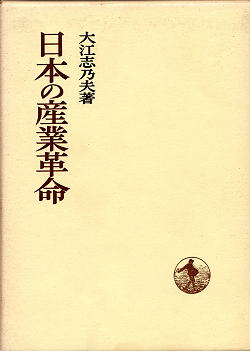
本書は、明治維新から、おおむね日露戦争期までの、日本の経済史を叙述しています。
おそらくは本書が出版された時期の時代性もあって、本書の記述には、「教条的」と感じられる用語もしばしば使われてはいますが、内容はきわめて学究的であり、また具体的です。石井寛治の上掲書と比べると、当時の統計資料からの引用がより豊富である点に、本書の一番の特徴があり、その点で、本書は価値を持っているように思います。
本書からは、本ウェブサイト中の以下のページで、引用等を行っています。、
横山源之助 『日本の下層社会』
初版 教文館 1899、岩波文庫版(改版)1985

日清戦後間もない1896(明治29)年から98(明治31)年にかけて、著者自身が、東京の貧民や職人、桐生・足利地方の織物工業や阪神地方の燐寸工場などの手工業労働者、大阪の紡績工場や東京の鉄工場など機械制工場の労働者、富山の小作人など、日本の労働階級の状況を実地調査し、分析・提言を行っている「報告書」です。
著者は、必ず、その産業に関する政府統計など、当時活用できた客観的・定量的な資料からマクロな状況を把握したのち、現場でのヒアリングで、統計数字には現れていない状況を確認し、総合的・ニュートラルに分析して、状況改善への提言を行っています。
岩波文庫の現行版のカバーには、「明治期ルポルタージュの白眉」と書かれていますが、これでは本書の性格を適切に表現しているとは言いがたく、誤解を招くおそれがあると思います。
「わが国の産業革命期における、新旧下層各層の生活・労働状態を、客観的かつ綜合的にあきらかにした社会学の古典である」(岩波文庫版、巻末の「小伝」)という評価が、やはり適切であると思います。日清戦争期の日本を理解するためには、必読書の1冊であるように思います。
本書は、本ウェブサイト中、下記のページで引用等を行っています。
● 4 日清戦争の経過 - 4b7 中盤戦⑦ 遼河平原と占領地
安藤良雄 編 『近代日本経済史要覧』
東京大学出版会 第2版 1979 (初版 1975)

堅苦しい書名で、中身のイメージが湧きにくいのですが、要するに、明治以降(一部幕末期を含む)の日本の経済統計資料集です。
国民総生産、鉱工業・農業生産指数、物価指数、貿易額、国際収支、人口などといった基本統計数字はもとより、様々な経済統計が網羅されています。さらに、例えば「五ヵ条の誓文」や「廃藩置県の詔書」などといった時々の重要資料の本文や、年表、内閣一覧、財閥企業系統図、政党系統図などの情報も一冊にまとめられています。
出版されたのが1970年代末ですので、その年代までの統計しか載せられていない、という制約はありますが、昭和の戦後期までの資料集としては、不都合はありません。
一方、政府の統計は、明治からの近代化が進むにつれて整備されて行きましたので、日清戦争当時の統計資料が、現在と比べると非常に少ないことはやむを得ません。それでも本書は、日清戦争以前を含め、日本の近代史を知るために必須の、基本参照資料である、と言えるように思います。
なお、この手の資料集としては当然のことですが、統計数字は「数表」で表されています。より理解しやすくするための「グラフ」化は、自ら試行する必要があります。
本書は、本ウェブサイト中、「4 日清戦争の経過 - 4c1 終盤戦① 澎湖島」、および「同 4e 戦闘の総括 戦費と戦死者」のページで引用等を行っています。
日本の鉄道発達史
『図説 日本の鉄道クロニクル (1) 汽笛一声 鉄道の誕生から私鉄王国へ 1853~1903』
講談社 2011
日本の鉄道史の入門書には、他にもっとよいものがあるかもしれません。たまたまこの本を見つけたので活用しました。「図説」であり分かりやすいので、初歩的な知識をてっとり早く得るのに役立ちます。
本書は、本ウェブサイト中、「2 戦争前の日清朝 - 2a4 日本④ 経済の状況」のページで引用等を行っています。
原田勝正 『明治鉄道物語』
筑摩書房 1983、講談社学術文庫 2010
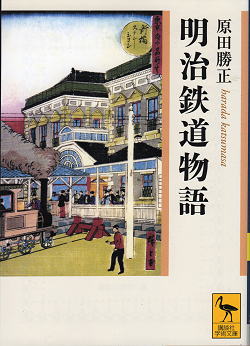
明治期の日本の鉄道建設の歴史について、機関車や車両、あるいは土木工事などの技術面から、鉄道運営の管理面、法制面まで、総合的に叙述した本です。
書名中の「物語」の語は、通史的でわかりやすいことを示すために使われていると思います。たしかに細かな注記はありません。しかし内容はなかなか詳細です。
幕末に欧米を訪問した日本人の鉄道体験から説き起こし、明治末年に日本が機関車の国産化を行って鉄道技術において完全に自立、また日露戦争に戦勝して日本国内と朝鮮・満州との能率的な輸送体系を構築し、さらにシベリア鉄道を介してヨーロッパへの連絡輸送が可能となったところまでの記述です。
本書は、本ウェブサイト中、「3 日本の戦争準備 3a 日本の軍備状況」のページで、引用等を行っています。
次は、日本国外の状況、すなわち、当時の帝国主義の状況と、日清戦争期の朝鮮および清国に関する参考図書・資料について、です。