8o 朝鮮内政改革と井上馨
日清戦争の宣戦詔勅で、日本は朝鮮の内政改革推進を公約しました。日清戦争期の朝鮮はどのような状況にあり、朝鮮の内政改革は具体的にどういう内容がどこまで行われたのか、内政改革を主導した井上馨はどのような人物であったのか、についての、参考図書・資料です。
このページの内容
朝鮮の内政改革について
井上馨について
● 世外井上公伝編纂会編 『世外井上公伝』 全5巻
(邦光史郎 『波乱万丈-井上馨伝』・海音寺潮五郎 『悪人列伝 近代篇』にも言及)
● 渡辺修二郎 『評伝 井上馨』・『対清対欧策』・『近世叢談』
朝鮮の内政改革について
朴宗根 『日清戦争と朝鮮』
青木書店 1982
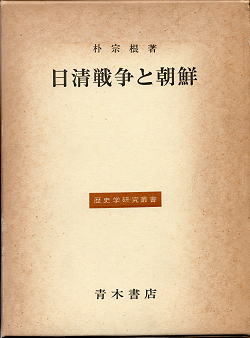
本書は、「日清戦争下の朝鮮」を主題とし、1894年4月の第一次農民戦争(東学乱)から96年2月の露館播遷事件までを扱っています。
日本の研究書ではあまり扱われていない、あるいは見落とされている点、例えば、開戦後の日本の対朝鮮政策と日本の利権追求や、第二次農民戦争と呼ばれる日清戦争下の反日蜂起、閔妃殺害・断髪令以後の反日義兵運動などが多く取り上げられている点で、本書は、日清戦争の研究者にとっては必読書の1冊であるように思われます。
閔妃殺害事件についての記述も詳しく、本書は、結論として三浦公使単独犯行説をとっています。
なお、著者には、「閔氏政権の崩壊過程-1894年の日・清両軍の出兵と関連して」(朝鮮史研究会論文集 第33集 1995 所収)などの論文もあります。
本書は、本ウェブサイト中、下記のページで引用等を行っています。
柳永益 『日清戦争期の韓国改革運動-甲午更張運動』
韓国での出版 1990 (翻訳出版 秋月望・広瀬貞三訳 法政大学出版局 2000)
本書の構成は下記となっています。
第1章 甲午更張をめぐる日本の対朝鮮政策
第2章 日清戦争中の日本の朝鮮保護国化画策と甲午・乙未更張
第3章 甲午更張以前の兪吉濬
第4章 軍国機務処の議案の分析
第5章 甲午開化派官僚の執権の経緯、背景および改革構想
朝鮮の内政改革は、日本の宣戦詔勅の宣言に従って、日本が主導して行ったものであるにかかわらず、その具体的な詳細の内容となると、日本の研究書にはあまり現れていないように思われますが、本書ではそこに焦点があてられています。
本書の巻末には、1895年3月30日の朝日借款条約や、井上馨が作らせた朝鮮で最初の近代的な国家予算である、1895年の予算書(英文)も、史料として掲載されています。特にこの予算書からは、当時の朝鮮政府の財政状況が具体的に数字で理解できます。
朝鮮での内政改革の具体的な内容を理解するためには、本書は、価値のきわめて高い必読書と言えるように思います。
本書からは、本ウェブサイト中の以下のページで、引用等を行っています。
森山茂徳 『近代日韓関係史研究』
東京大学出版会 1987
本書には、井上馨による朝鮮内政改革に関する記述もありますので、ここに挙げておきます。
本書自体は、日清戦争から日韓併合までの時期の日韓関係に関する研究書であり、の3つの視点から論じられています。
第一に、如何にして保護化、併合に帰着したのか、日本の政治指導者たちの抱いていた選択肢の競合の視角から、
第二に、朝鮮の政治指導者たちが推進した独立維持のための内外政策、何ゆえ挫折したのか、選択肢および競合関係から、
第三、東アジア国際関係、欧米列強間に存在したメカニズムの変化、何ゆえ如何にして起こったのか
本書からは、本ウェブサイト中の以下のページで、引用等を行っています。
井上馨について
世外井上公伝編纂会編 『世外井上公伝』 全5巻
内外書籍 1933‐34 (『明治百年史叢書』 原書房復刻 1968)
朝鮮公使として京城に赴任し、内政改革を主導した井上馨の伝記です。史料をそのまま引用している箇所が、かなりあり、その点で本書は、多少読みにくいところがあるものの、内容的にはなかなか優れている、と言えるように思います。朝鮮公使時代については、第4巻に出ています。
本書は、復刻版が出版されているほか、国立国会図書館デジタルコレクションで読むことが出来ます。
新しい本ではありませんし、5巻もあるので、全体を通読しようという意欲が湧きにくいことは間違いありません。もっと手軽に読めるものはないのか、という気になります。しかし、次に挙げる堀雅昭 『井上馨』が2013年に出版されるまでは、井上馨の全生涯を扱った伝記は、本書しかありませんでした。
邦光史郎 『波乱万丈-井上馨伝』(光風社出版 1984、大陸文庫 1989)という本はあります。しかし、この本では、幕末期1862(文久2)年から、維新後いったん政府から退いて実業界に入り、再び請われて1875(明治8)年江華島事件の処理で政府に復帰するまでの、井上馨の20代後半から30代後半までの時期だけが描かれており、外務卿などで活躍した後年は、日清戦争期を含め、対象外となっています。
井上は、「金にかんして嗅覚がきく」ところがあったようで、そのために明治6年に「尾去沢銅山横領事件」を起こして追及され、政府から一旦は退くことになりました。海音寺潮五郎の『悪人列伝 近代篇』(文芸春秋 1961-62、文春文庫)の中に井上馨も取り上げられているのは、井上が「維新政府の藩閥を土台とする貪官汚吏の代表者」として扱われているためです。当時、そういう人物は井上だけではなかったろう、と思われるのですが。
明治天皇も、井上が「狡猾なるをご存じにて御嫌い」(明治天皇の侍補であった佐々木高行の日記、色川大吉 『日本の歴史21 近代国家の出発』 から孫引き)であったということなので、人格者とはとても言えないようです。
鹿鳴館を建てて極端な欧化路線をとったりしたこともあって、一般的には、どうも評判が良くない人ではあります。日清戦争直前の議会でも、井上は昔の疑惑を追及されています。
しかし、他方では、三井物産の前身となった商社を起業した人であり、また財政・経済に関して深い知識があり、かなり健全な発想をしていただけでなく、優れた実務能力も持っていた人のように思われます。外交についても、世界情勢をよく理解していて、現実的かつ協調的な姿勢が強かったように思われます。
すなわち、人格的にはともかくも、近代化・資本主義化の道筋や、その実現に必要な政策とその実務について、他の人々よりは、よほど的確な知識と判断力があった人物のように思われるのです。
本書からは、本ウェブサイト中の以下のページで、引用等を行っています。
● 6 朝鮮改革と挫折 - 6b 井上馨による朝鮮の内政改革
堀雅昭 『井上馨 - 開明的ナショナリズム』
弦書房 2013

上述の 『世外井上公伝』 は「資料の寄せ集め集」で、「新資料の発掘や子孫縁者からの取材を加えた評伝はおそらく本書が最初」(本書の「はじめに」)というのは、その通りだと思います。
本書は、1冊で井上馨の全体像を効率的に理解できます。また、『世外井上公伝』 では取り上げられていない資料に基づく記述が、非常に豊富です。大変に良い本が出版されたと思います。
ただし、260ページほどの本文に、井上馨の全生涯が押し込まれています。そのため、大部の 『世外井上公伝』 では詳細に触れられているのに、本書ではほとんど言及されていない事項は、少なくありません。
したがって、井上馨を詳しく知りたい人にとっては、本書が出たから 『世外井上公伝』 は読む必要がなくなった、とは言えません。両方を読んで初めて全体像が理解できるように思います。
たとえば、朝鮮公使時代について、『世外井上公伝』 では史料も使って詳しく記述されていますが、本書ではかなり簡単に済まされています。しかし、本書でも、その時期について目を引く記述があります。
例えば朝鮮公使を引受けたことについて、鮎川義介がその著書で、井上馨は「人のいやがる損な役を買って出る特徴があった」と述べていること、また井上馨自身が、殺害された閔妃について、「決して世人の思うような悪い婦人ではない」、「妖婦独婦などと称すべき婦人ではない」と述べ、その一方で大院君については、「これはなかなか喰えぬ爺さん」と言っている(明治29年5月12日 『読売新聞』)こと、などです。
著者は、本書の副題に、「開明的ナショナリズム」という言葉を使っています。これは、「従来の欧化主義者のレッテルを剥がし」、江藤淳の言った「開かれたナショナリズム」の実践者であることを示すために著者が選んだ言葉であるようです。
井上馨の「開明的ナショナリズム」の具体的な在り方として、著者は、① 「西洋流の近代資本主義の構築こそが、世界と向かい合える唯一の手段である」と認識していたこと、② 方針の設定や行動においてリアリストであったこと、③ 「生涯、非戦論の立場を基本」にして「国際協調路線を貫いた」こと、などを挙げています(本書の「はじめに」)。
著者の井上馨に対するこの評価は非常に的確であるように思います。ただし、これを一言で表すのに、「開明的ナショナリズム」という用語が最適であるかどうかは、議論の余地があるかもしれません。筆者は、「富国主義者のナショナリスト」という言葉の方が的確のように感じていますが、いずれにしても、その本質については、著者の見解は誠に至当という気がしています。
実際、本書を通読して、井上馨という人物が、多くの企業設立や経済プロジェクトに関与していた点に、あらためて強い印象が残りました。近代化の本質は産業の発展にあることをよく理解した上で、財政・経済の実務についても良く承知していて、産業の発展を積極的に支援することが自らの行動・実践の重要な部分であると意識していた政治家であった、と言えるように思います。
なお、本ウェブサイトの本文中では、本書からの引用等は行っていません。
渡辺修二郎 『評伝 井上馨』
同文館 1897
本書の存在は、上掲の堀雅昭 『井上馨』 から知りました。明治30年1月、井上馨が朝鮮公使を退任してから2年ほど、というタイミングで出版されたものです。本書も、国立国会図書館のデジタルコレクションで公開されています。よく知られている本ではないと思いますので、以下に少し詳しくご紹介します。
『評伝』 という表題ですが、徹底した井上馨批判の書です。「井上馨の外政におけるが如き、その拙弱を極る、… 国事を誤る者は実に閥老なり。吾人日本人の大義においてこれに筆誅を加えざるをえず。井上馨評伝を作る」というのが本書の目的であるようです。
全体として、尾去沢銅山事件・藤田組贋札事件・条約改正など、悪行と思われることは詳しく記述するが、そうではないことにはあまり触れない、というのが本書の特徴です。
この著者の井上馨に対する根本的な評価は、「井上馨の歴史は失敗の歴史なり … 彼の事績中一、二を除くのほか、ほとんど見るに足るものなく、強いてこれを求めれば伊藤と共に政治を腐敗せしめ、社会を攪乱したるの事あるのみ」というものです。伊藤博文に対する評価も厳しいようです。
朝鮮関係については、「外務長官井上の朝鮮に対するの政策は一貫せずして、常に変転せり」とは述べているものの、どう一貫しなかったかには触れられず、壬午軍乱・甲申事変から東学乱に至るまで、「例のごとく平和説」である点が非難の対象となっています。
朝鮮公使時代については、「朝鮮における彼の施為は失敗中の失敗なり。… 井上もまた王妃に籠絡せられてその薬籠中の物となりしを自ら知らざるなり。…王妃性妬悍巧慧にしてその機智才略井上老人の能く及ぶところにあらず」などとして、失敗の原因が必要不可欠な資金供与を行わなかった日本政府側にあったことには一切触れず、井上馨が閔妃に籠絡されたと、事実とは異なる推量に基づいて評価を下しています。
ただし著者も井上の功績を一切無視しているわけではなく、「井上の官歴中成績ありしものは、廃藩後民政と財務を整理統一したるの一事あるのみ」とし、あるいは、「彼の成績はむしろこれを民間における事業中に求るを得ん。彼は政治家たらんよりも、比較上むしろ商業者たるに適す」と述べています。財務・経済に強いことは認めるものの、それには価値は置けない、というのがこの著者の考え方のようです。
この著者が、なぜここまで井上馨を非難しているかについては、同じ著者が本書の3年前に書いた『対清対欧策』(奉公会 1894)を読んでみて、よく理解できました。本書も、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されています。本書の本文末尾に、「27年11月22日即ち我が軍旅順口略取の日擱筆」とあり、下関講和談判の4か月近く前、日清戦争がまだまだ続いてゆく時点で書きあげられ、すぐに出版されたものです。
本書の中で著者は、日清講和の条件として、① 少なくも台湾及び盛京、直隷、山東、江蘇、浙江の土地の日本への割与、② 軍艦砲銃の大部分を日本に譲与、③ 十分の償金、④ 今後朝鮮の国事に干渉せざることの誓約、⑤ 旧締日清条約を改定して十分の権理と利益を日本に収むる事、の5条件を挙げています。④・⑤は必ず実現すべき条件であり、③については、「実費に数倍」の償金を要求するものとするが、①または②の達成度によっては減額しても良い、としています。
著者は、この講和条件を達成するために、「騎虎の勢止めんとして止まるべからず。… もはや他国の仲裁調停を容るるの余地を存せず」として、今後は外国からの仲裁・調停の申入れなどは一切拒否して、戦争を続行せよ、と主張しています。
この、領土をできるだけ広げたいという願望について、著者自身も、「ただ憾む(うらむ)らくは、艦船多からずして同時に彼の東南海岸を攻略するの自由に乏しきことを」として、艦船の能力が不足していることを気にしてはいますが、6個師団しかない日本陸軍の現実の戦力や、これだけ領土を拡げようとすれば必ず直面するに違いない兵站補給能力とそれを支える軍費調達問題などは、一切捨象されています。
非現実的としか言いようがない領土拡大に、著者がここまでこだわっている理由は、「我が帝国の盛運を益し、よりてもって世界の形勢を一変せしめ、独り東洋のみならず全世界に覇たること、これより期すべく」と、見ていることにあります。すなわち著者は、世界の中での国家の評価は、どこまで「覇たる」かによって決まる、と認識していたようです。19世紀帝国主義時代の世界観であるよりも、15~16世紀の大航海時代的な世界観を思わせます。
すなわち、渡辺修二郎という著者は、近代化の本質を全く理解しておらず、前近代的な正邪の価値観に基づく観念的な志向が著しく強い、実務家とは程遠い存在であったように思われます。また明らかに、過剰なナショナリスト、自国独善主義の人であったと言えそうです。この当時の対外硬論者の一つの典型例なのかも知れません。
この著者の略歴は、晩年の著書『近世叢談』(北海出版社 1944年)に出ていると、「横浜開港資料館」のウェブ・サイトから知りました。それによると渡辺は、1855(安政2)年生まれで、明治10年前後の時期に、東京英語学校(一高の前身)や立教学校(立教大学の前身)で外人教師から英語を学び、仙台中学や学習院で英語の教師をしていたことがある、という人物なので、英語力は高かったようです。
それゆえ、海外の報道などについての知識も持っている点は、国内しか知らぬ対外硬論者とは大いに異なるところですが、著者は、列強の考え方について、読み違えをしています。イギリスは日清戦争によって貿易上最も不利となるので、列国共同での調停を提案し、ドイツはこれに乗るかもしれないが、フランス・アメリカは乗らない、ロシアはシベリア鉄道の開通までは動かない、「到底強制的仲裁の同盟、容易に結び得べからず」と述べていますが、これは願望思考で判断したものというのが妥当でしょう。著者のこの読みは全く外れました。外交をはるかに良く知る井上馨が心配した通りに、干渉が現実化し、しかもドイツとロシアが主導してフランスがそれに乗る形での三国干渉となりました。
一方、著者は、ただ単に威勢が良いだけの他の対外硬論者とは異なる、なかなか的確な判断を行っている点もあります。一つは、「支那を攻伐するにつきては、次に欧州の一国と交戦するの時機あるべきを覚悟なかるべからず」と述べていることです。日清戦争の結果はかえって列強による中国分割競争を生じるので、その中で日本は欧州の一国と交戦せざるを得なくなる、との認識は、非常に的確なものであったといわざるを得ません。ただし著者は、その相手はイギリスになるだろう、と見ていました。
もう一つは、そのイギリスについて、「英は実利を見るに敏なるの国なり。清人の怯弱なること意想外なるに驚き、清の頼むべからざるを見て、清をもって露に対するの藩屏とするに足らざるを知り、今や大に昨非を悔悟し、幡然として方向を改め、清を去り日本に就くの事なしと云うべからず」として、将来の日英同盟の可能性を指摘している事です。まさしくその通りになりました。著者の列強理解が全くの見当外れではなく、それなりのレベルにはあったことを、良く示していると思います。
列強からの干渉について、著者の読みは全く外れ、井上馨の読みがはるかに正しかったわけですが、3年後の 『評伝 井上馨』 では、著者にその反省は一切なく、相変わらず井上の「平和説」への攻撃を行っていた、ということになります。すなわち、渡辺修二郎の 『対清対欧論』 と 『評伝 井上馨』 からは、「強兵主義者」の過剰なナショナリスト対「富国主義者」のナショナリストの対立が見えてきます。
「強兵主義者」は、観念的に「覇たる」ことが正であるとして、「強兵」にこだわっています。「富国主義者」は、そんなことをすれば財政的・経済的に「貧国」から抜け出せず、長期的な視点からはかえって「強兵」が果たせなくなると指摘しているのですが、前近代的な固定観念に邪魔されて、「強兵主義者」にはそれが理解できません。
近代化の本質をより的確に理解していた「富国主義者」にとって、国力を世界に示すこととは、産業発展・貿易拡大による「富国」の達成を世界に示すことであり、その実現には国際協調で平和が維持される方が有利である、という現実的な判断があります。
しかし、観念的に「覇」たることを正とする「強兵主義者」の立場からは、国際協調は許せるものではなく、「富国主義者」の「平和説」をひたすら非難していた、という姿が浮かび上がってくるように思いますが、いかがでしょうか。
渡辺修二郎は、せっかくこの時代に英語を身に着けていたのに、観念的な「強兵主義者」になってしまいました。同様にこの時代に英語が得意であった他の多くの人々との最大の違いは、渡辺が、歴史には関心が高いものの、経済や産業・科学といった、近代化の本質でありその象徴でもある事物には、ほとんど関心を示していない点です。英語は身に着けたものの、若いうちに実際に海外に出て、欧米の状況を実見する機会に恵まれなかったことが大きな差になってしまった、という気がします。
なお、本ウェブサイトの本文中では、本書からの引用等は行っていません。
曽根松太郎 『当世人物評』
金港堂書籍 1902年
著者名は曽根松太郎となっていますが、ウィキペディアによれば、『当世人物評』 は、元はジャーナリストの石川安二郎(号は半山)が、横浜毎日新聞に1899~1900(明治32~33)年に連載したもののであるとのこと、また「ハイカラ」という言葉も、この記事中で使われ始めた言葉であるとされています。本書も、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されています。
本書には、伊藤博文、大隈重信、西郷従道、渋沢栄一、田口卯吉など、全部で13人の人物評が含まれており、井上馨もそのうちの一人です。上掲の渡辺修二郎の 『評伝』 から5年後の出版ですが、ほぼ全く対照的な評価となっています。
まずは、財政上での井上馨の評価について。
● 財政家としての井上伯は、常に消極的方針に傾いている。… 明治6年5月に渋沢栄一君と共に有名な意見書を出して、その大蔵大輔の任を退いた時も、全く国費のいたずらに膨張するを慷慨したもの。…
● 明治30年の春、第三次伊藤内閣の出来た時、25年ぶりで財政の当局者となったが、この時にも依然として消極方針を取った。… 出来得る限り節約を実行し、なお不足の所はやむを得ず、増税するという方針、… この財政計画は吾輩の如きも、熱心に賛成した一人で、この時代においては、最も適当な処置であった。
ここで言われている「消極的方針」は、現代語では、「財政健全化方針」と表現するのが適切と思われます。本書の著者も、井上の方針を支持しています。
次に、外交分野での井上の評価についてです。
● 吾輩の見るところをもってすれば、彼の条約改正案も…敢えて不当の案件でもなかったのみならず、この〔明治13年9月~20年の9月の井上馨が外務の当局者であった〕7年間において、彼が国家に貢献した功労は、実に偉大なるものである。第一に公使館、領事館の数は、彼の在職中に著しく殖え、日本の交際範囲が、著しく拡張せられた。第二に朝鮮事件は、花房公使の時も竹添公使の時も、… これらの事件に対する彼の処置は、一も非難すべき点を見ない。
● 彼の名は、明治の外交史において、特筆大書すべきものに相違ない。… 特に日清戦争の前後において、身を挺して朝鮮公使となり、その威望この半島の上に輝き、彼の在任中は半島に何等の紛擾をみざりしが如きは、彼が外交家としての手腕の非凡なりしを証するものである。
そして、井上馨の経済界との関係について。
● 彼はまた経済界の一大勢力である。かつて自ら先収会社を起こし、その総裁となって、商業界の大勢力となり、明治8年大阪会議の結果、再び政府に入って後も、なお東には三井組の顧問となり、西には藤田組の相談役として、20年間1日の如く実業に関係し、彼の一顰一笑が、今もって実業界に大影響を与うるところ、真に経済社会の一大勢力である。
● 今の元老中において、経済社会における勢力が、彼に匹敵すべきは、ただ松方伯のみで、その余は何人といえども彼の向うに立つことはできない。
最後に著者は、井上馨の人材抜擢と部下への態度について、長所と短所を挙げています。
● 一言すべきは、彼が能く後進を抜擢することで、… 彼の如く多くの人材を政府に引き入れた者は、他にその比を見ない。
● 彼のために惜しむべきは、彼が余りに強い癇癪を起こすことで、せっかく彼に抜擢せられて、その恩を受けた者も、彼が癇癪を起してこれを痛罵するために、遂に彼を去って他の元老に赴くに至る。
● 井上伯が失敗の事績多く、世人に誤解せられている点の多い如きも、全く彼が情の人であることを現しているゆえんで、その失敗の多きにもかかわらず、未だその朋友に捨てられず、依然として、朝野に重きを置かれているのは、明らかに彼の言行に真情の流露するところがあって、人をして彼を憎むに忍ばざらしむるがためであろうと考える。
全体に井上馨の肩を持ち過ぎ、という感もないではありませんが、渡辺修二郎の 『評伝』 よりは、はるかに客観的な評価ではないか、という気がします。経済・外交のみならず、人材育成についても大いに力のある人物であったが、人格上の問題もあった、というのがこの著者の井上馨への評価、ということになるかと思います。
なお、井上馨の財政・経済面での重要性については、西野喜与作 『半世紀財界側面誌』(東洋経済出版部 1932)でも触れられています。本書の内容は、もともと時事新報に連載された記事を主としたものである、とされています。本書も、国立国会図書館デジタルコレクションで公開されています。
本書によれば、明治15年ごろ、政府の「経済政策の枢機を握っていた第一人者は大蔵卿たる松方正義」であったが、松方に次いだのは、「農商務卿たる西郷従道、工部卿たる佐々木高行」ではなく、両省の大輔である品川弥二郎と井上勝にあり、「井上勝や品川の背後にあって糸を引いていたものは外務卿たる井上馨であった。」
井上は、「松方に対抗する大勢力」であり、「民間にも渋沢栄一や三井家 ― 特に益田孝― や廃藩置県以来封建国守から資本家に変質した毛利家や、大阪の藤田伝三郎などを通じて一大勢力」をもっていた。
井上はその後も、「政治上の立場の利不利にかかわらず、関係財閥の繁栄とともに、死するまで我が財界に偉大なる潜勢力をもっていた」。井上は、大蔵省や農商務省のポストに就いた期間はごく短く、「財政経済上の官暦に関する限りはすこぶる貧弱」。ところが、「一介の浪人として内田山の屋敷に寝転んでいても、財界を動かすだけの力を持っていたのだから偉い。制度や職掌を超越した一大存在である。」
『当世人物評』 において、外交上の評価よりも先に、その財政上の評価が論じられているところ、またこうして、『財界側面誌』 という表題の本にも取り上げられているところが、井上馨の井上馨たるところ、と言って良いのではないか、と思います。
なお、本ウェブサイトの本文中では、本書からの引用等は行っていません。
小島直記 『出世を急がぬ男たち』
新潮社 1981年
本書も、上掲の堀雅昭 『井上馨』 から、その存在を知りました。ページ数としてはごくわずかですが、本書中に井上馨への言及があります。経済分野を得意とする作家の本領発揮で、井上馨を良く知る財界人などからの井上馨への評言が集められています。
例えば、三井の総帥であった池田成彬の、「当時財界で井上の傘下に入っていないのは三菱ぐらいのもので、大阪の住友、鴻池、九州で貝島、東京で三井 … それから日銀、〔横浜〕正金、その他の特殊銀行はほとんど全部が井上さんの支配 … それだから、… 井上さんの前に出ると … 渋沢さんでさえ、もみ手をして… かしこまっている」という証言を引き、小島は、「『日本財界の最高指導者渋沢栄一』という定説が、単なる虚像にすぎないことを一言で喝破している。最高指導者は井上だったのだ」と結論しています。
「伊藤、山県、松方、大隈等々、多くの高官・元勲の中で、なぜ井上だけがこの地位をかち得たのか」について、小島は、「井上自身、財界の指導者にふさわしい努力をいろいろとやったのである」として、個別企業(とくに三井系)に経営関与したこと、財界有力者を集めて、井上の指導下に経済研究をする会を組織したこと、企業の工場を頻繁に巡視したことなどを挙げ、「こういう努力は、他の元老たちはだれ一人やらなかった」と、評価しています。
「しかしながら、この努力によってせっかく獲得した最高指導者の椅子にもかかわらず、本当の権威は生じなかった。そこに井上の人間的悲劇がある」というのが、小島が井上について言いたかったもう一つの大きな点のようです。
例えば、鐘紡の経営者として有名な武藤山治の、「井上侯は物事を総合的に判断なさらないご性質で…」というコメントを引き、「井上の経営判断力が貧困だったことをいっている」と指摘しています。どうも井上は、細かいところに突っ込み過ぎ、「木を見て森を見ず」的な判断に陥ることがあったようです。朝鮮公使時代にも、この点が少し表面に出たところがあったもしれません。
小島は井上の晩年について、「努力をし、かつ謙虚であったのならば文句はないが、努力をし、その上で増上慢におちいったのである。そっくり返り、わがままになり、汚くなった。ことにひどかったのが他人所蔵の骨董品に対する態度である」として、気に入った骨董品を見るとすぐに人から取り上げたという証言をいろいろ引いています。井上は「老年の栄光」に輝いてはいたが、その裏面には、「世間の軽蔑、井上自身の自覚せざる老醜の悲惨さ」があった、というのが、井上の晩年に対する小島の結論です。
なお、本ウェブサイトの本文中では、本書からの引用等は行っていません。
以上、井上馨に関する本・資料を挙げました。その内容を少し詳しくご紹介しましたのは、井上馨の朝鮮公使時代の事績については、今までの研究が、井上馨の全体像を見たうえで評価していないため、少し誤解を生じているのではないかと思われるためです。
井上馨は本質的に「富国主義者」であったと言って良いように思われます。人格には多少の問題があったようですが、近代化の本質が経済発展にあることについては適切に認識して、その基本的認識に立脚した政策を実行し続けた人物、と言えるのではないでしょうか。
ところが、このウェブサイトの本文に書きました通り、井上馨は、韓国の研究者の一部からは、本質的に対外強硬論者との扱いをされたり、閔妃殺害の黒幕扱いされたりして、明らかに評判が良くありません。それだけでなく、日本の研究者からも、朝鮮内政改革の失敗について、日本政府側、とくに陸奥宗光に大きな問題があったことは全く捨象され、その責任を一方的に押し付けられているような観があります。
堀雅昭 『井上馨』 のような良い本が出てきましたので、今後は井上馨についての研究がもっと活発になっていくことを願っています。
次は、本ウェブサイトの最終ページになりますが、便費殺害事件関係の参考図書についてです。