8g 軍事史・軍事戦略の研究
日清戦争の軍事的な側面を理解しようと思うと、時間的には明治から昭和前期までの日本の陸海軍の歴史的な経緯の中で、地理的には世界的な観点からの見方も含めて、広く軍事史や軍事戦略の全般の展開の中で、日清戦争の位置づけを確認する、という作業も必要になるように思います。
そうした軍事史・軍事戦略に関する図書のうち、本ウェブサイトで参考にしたものを以下に挙げます。昭和前期までの日本の師団の歴史、軍事予算や軍備の歴史、鉄道の軍事利用の歴史、日本の歴代の陸海軍大将、軍事戦略思想史などについての日本国内の著作のほか、軍事史・軍事戦略などに関する海外の著作が含まれます。
このページの内容
日本の師団の歴史、軍事予算や軍備の歴史、鉄道の軍事利用の歴史について
歴代の陸海軍大将、軍事戦略思想史などについて
軍事史・軍事戦略などに関する海外の著作
日本の師団の歴史、軍事予算や軍備の歴史、鉄道の軍事利用の歴史について
近現代史編纂会編 『陸軍師団総覧』
新人物往来社 2000
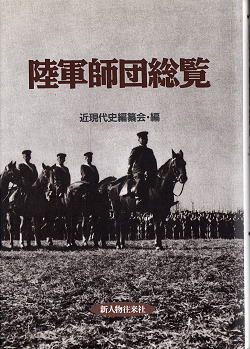
まずは、日本陸軍の基礎知識に関する本です。
前半では、内務班-中隊-大隊-連隊-旅団-師団という師団の構成と人数、将校・下士官・兵の階級と昇格、軍内の教育、兵役とその期間などが分かりやすく整理されています。
つまり、例えば「歩兵大隊」といえば、1個約200人弱の中隊が4個(平時は3個)に歩兵砲中隊や大隊本部まで加わって、合計1100人弱で、大隊長は中佐、などという、軍隊の基本常識を教えてくれる本です。
後半では陸軍の各師団について、創設日や編成地、歴代の師団長名などの基本情報と、戦歴が整理されています。
筆者は、たまたま本書を参考にしましたが、他にもっとよいものがあるかもしれません。本書からは、本ウェブサイトの本文では何も引用等は行っていませんが、戦争の経過を理解するには、本書のような日本陸軍の基礎知識の解説書をあらかじめ読んでおかないと、なかなか理解が難しいという気がします。
山田朗 『軍備拡張の近代史 - 日本軍の膨張と崩壊』
吉川弘文館 1997
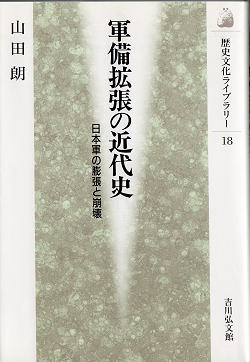
本書の「はじめに」の中で、著者は、本書は「近代日本の軍事力の歴史」を描こうとするものであり、「戦争でないときに軍事力がどのような考え方で、どれほどのエネルギーを費やして建設されたかに焦点を当てている」としています。
日本の軍事費統計を始め、いろいろな資料も掲載されており、役に立ちます。
なお、日本の軍事力の歴史について、「陸軍の歩兵中心・白兵主義と海軍の大艦巨砲・艦隊決戦主義は、官僚的なセクショナリズムにも助けられて揺るぎのないものとなり、それらに基づく作戦構想への固執がとめどもない軍拡をもたらした」、「国家も軍隊も、ただひとつのシナリオしかもたない硬直性は、現実世界を観察する眼を曇らせ、将来に対する洞察力を育てることを阻害」した、という著者の評価は、説得力があります。
本書からは、本ウェブサイト中、下記のページで、同書中のデータの利用や引用等を行っています。
熊谷直 『軍用鉄道発達物語』
光人社 2009
本書の著者は防大卒で、自衛官から防大助教授、防衛研究所戦史研究部所員などの経歴があり、定年退官後は、軍事史家、軍事評論家という人です。「物語」という書名示すように。読みやすく書かれています。
1866年の普墺戦争、1970年の普仏戦争での鉄道利用から話がはじまり、世界の動向と日本の状況の両方が押えられています。世界については、ロシアのシベリア鉄道や、第一次世界大戦での欧州各国の鉄道活用状況などが、記述されています。
日露戦争中の日本陸軍の鉄道活用状況については、このウェブ・サイトの本文で引用しました。日清戦争で最初の軍事輸送を行った経験を出発点に、以後、日露戦争期から大東亜戦争に入る前までは、鉄道線路や運用方法について次々にカイゼンを重ねていった経過が、本書からよくわかります。
大東亜戦争期、中国やインドシナ半島では、欧州勢によりすでに敷設されていた鉄道の活用なしには、日本軍の緒戦の迅速な作戦は成り立たなかったこと、逆に鉄道がなかったガダルカナルやニューギニア、インパールでは、補給手段がないために日本軍将兵が飢えに苦しめられたこと、日本陸軍では自動車の発達が遅れていたために泰緬鉄道の新設で鉄道聯隊が苦労したこと、また戦時の人員物資の輸送に貢献するための鉄道が、物資不足により日本国内でも輸送力減少、輸送スピード低下を起こしていたことなども指摘されています。
昭和前期の敗戦後については、占領軍による鉄道管理や、占領軍用の輸送体制、昭和35年に設立された陸上自衛隊の鉄道部隊についても触れられています。その鉄道部隊が、昭和41年に、より近代的なミサイル部隊やヘリコプター部隊の整備のために整理されてしまうところで、本書は終わっています。
本書からは、本ウェブサイト中、下記のページで、引用等を行っています。
歴代の陸海軍大将、軍事戦略思想史などについて
半藤一利・横山恵一・秦郁彦・原剛 『歴代陸軍大将全覧』
全4冊 (明治篇・大正篇・昭和篇 上・昭和篇 下) 中公新書ラクレ 2009

日本陸軍の基礎を作った大村益次郎と、最初の陸軍大将である西郷隆盛以来の、歴代の陸軍大将の全員について、その一人一人の人物や業績を、半藤一利らの4人が論評し合う、という内容の本です。戦史で名前が出てくる軍人は、その人物の一生を通してみるとどういう経歴であったのか、どういう人物であったのか、がよく分かります。
それぞれの巻末に、各陸軍大将の経歴表が掲載されています。誰が何篇に出てくるかは、大将に任官された時期によります。日清戦争で活躍した軍人は、将官は明治のうちに、士官は大正のうちに、陸軍大将になっていますので、日清戦争に関してだけなら、明治篇・大正篇だけを読めば済みます。
昭和篇まで読み通すと、各時期で、軍人の傾向が少しずつ変化していったのが、何となく分かったような気になります。
本書は、本ウェブサイトの下記のページで、引用等を行っています。
● 4 日清戦争の経過 - 4b2 中盤戦② 九連城より清国内へ
半藤一利・横山恵一・秦郁彦・戸高一成 『歴代海軍大将全覧』
中公新書ラクレ 2009

上掲書の海軍版です。
日本海軍の基礎を作った勝海舟と、最初の海軍大将である西郷従道以来の、歴代の海軍大将の全員について、その一人一人の人物や業績を、半藤一利らの4人が論評し合う、という内容の本です。論評する4人のメンバーのうちの1人が、陸軍版から入れ替わっています。
全部で4冊の陸軍版と違い、海軍版は1冊にまとめられています。そのため、陸軍版より本が多少厚くはなっています。しかし、結果的に、一人一人に対する論評の量が、陸軍版よりかなり減らされています。その点は、誠に残念です。
本書は、本ウェブサイト中、「4 日清戦争の経過 - 4d 台湾征服戦」のページで引用等を行っています。
前原透 『日本陸軍用兵思想史』
天狼書店 1994
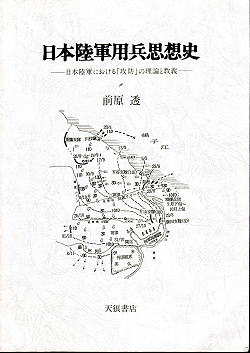
著者は、昭和前期の敗戦の年の陸士卒、その後陸上自衛隊で防衛研究所戦史部所員でもあった軍事史研究家です。
日本陸軍の用兵思想あるいは戦略・戦術思想として特徴的なことは、「攻撃・攻勢主義」「火力軽視・白兵突撃主義」「精神主義」などにありましたが、とりわけ昭和前期の日本陸軍では、攻勢・攻撃以外全く考えられない状態に硬直し、最終的には「大日本帝国」を攻勢的政策のうちに崩壊させた、との問題意識から、その根源の追求を行ったのが本書です。
著者は、日本陸軍創設以来の、『歩兵操典』 をはじめとする典範令や陸軍部内の兵学に関する文書を一つ一つ検討しています。
明治初年にフランス式の翻訳で始まった陸軍の用兵思想は、その後ドイツ式に切り換えられ、また、当初は攻勢・守勢が冷静至当に論じられていたものが、だんだん攻勢に強調を置くように変わっていったようです。
最大の変化は日露戦後で、ドイツ歩兵操典の翻訳から脱却し、わが国独自の 『歩兵操典』 が作られ、その際に、攻撃精神を基礎とし、白兵主義が採用されたこと、また一旦占有せる地区は尺土といえども、再びこれを敵に委すべからずなどという規定も作られたこと、などが論証されています。
本書は、本ウェブサイト中の下記のページで、引用等を行っています。
軍事史・軍事戦略などに関する海外の著作
浅野裕一 『孫子』
講談社学術文庫 1997
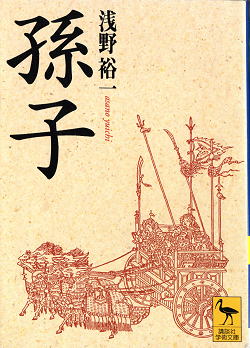
日本陸軍の戦い方が妥当であったかどうか検討するには、孫子を読んでみるのも、重要作業の一つと思われます。昭和前期の陸軍は、孫子を読んではいなかったことが、よくわかります。
孫子については多くの書があるなかで、たまたま手にとっただけの本ですから、他にもっとよい本があるかもしれません。本書は、前漢時代のテキストに基づくもので、もともと 『中国の古典 孫子』 として1986年に出版されたものが、97年に学術文庫化されています。
孫子の各段単位で、最初に現代語訳、次に漢文の書き下し文、それから元の漢文と語句注釈、最後に解説、という順序で、全13篇が訳されています。
巻末には、『孫子』がいかに成立したかを述べ、また近代の西欧兵学にはどのような影響を与えてきたかも触れている解説が付されています。
本書は、本ウェブサイト中、「4 日清戦争の経過 - 4b4 中盤戦④ 旅順虐殺事件」のページで、引用等を行っています。
マーチン・ファン・クレフェルト (佐藤佐三郎訳) 『補給戦-何が勝敗を決定するのか』
中公文庫 2006 (単行本 初刊 原書房 1980)
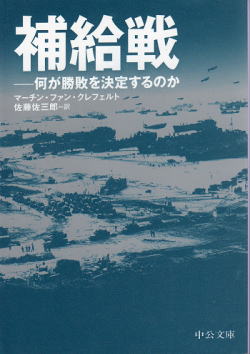
原著は、 Martin van Creveld, Supplying War, 1977。本書の主題は、「軍事史家によってしばしば無視」されている、軍隊への補給問題、すなわち日清戦争でもカイゼンが必要な重要課題であった兵站輜重問題です。
16世紀中葉のスペインによるオランダの反乱抑圧戦から始めて、とりわけ19世紀以降にページ数が大きく当てられ、ナポレオン戦争、プロイセンの普墺・普仏両戦争、第一次世界大戦の西部戦線での電撃戦、第2次世界大戦でのドイツの対ソ戦・ロンメルの北アフリカ作戦・連合軍のノルマンディ上陸作戦などでの軍事補給の実態が、具体的に論じられています。
平壌戦での野津師団長のような悪い例もあったものの、日清戦争での日本軍は、概して補給に非常に大きな努力を行い、カイゼンに努めていたと言えることが、こういう本の記述と対比することで、確認できるように思います。
それと比べて、昭和前期の日本軍は、どうして補給への関心をほとんど払わなくなってしまい、無理な作戦を重ねたのでしょうか。この点で、日本軍には著しい劣化があり、昭和前期の戦争は負けるべくして負けた、と言わざるを得ないように思います。
本書は、本ウェブサイト中、以下のページで引用等を行っています。
ポール・ポースト (山形浩生 訳) 『戦争の経済学』
バジリコ 2007
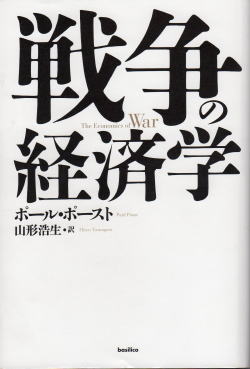
原著は、Paul Poast, The Economics of War, 2006。
末尾の「訳者解説」に、本書は、戦争について簡単な経済理論を使って分析することで、総合的に考える枠組を提供しようというものであるが、簡単な経済理論を説明するため戦争を題材に使った本でもある、とあります。まさしくその通りの内容です。戦争や軍備に対する左右の特定の観念を前提にせず、すなわち正邪論におちいることなく、現実のデータに基づいて一貫して定量的に分析しているところに、本書の良さがあると思います。
本文でもご紹介した「戦争の経済効果」のほか、「軍隊の経済学」、「安全保障の経済面」が論じられています。具体的には、徴兵制の場合と志願制の場合の費用と効果の差、防衛産業と通常の産業の相違や、内戦やテロリズムまで、戦争と軍事に関する幅広い内容が経済学的に論じられています。
もう少し具体的に見てみると、例えば総志願制と徴兵制の費用対効果の対比では、総志願制の軍隊では、兵員に民間と競合できるだけの賃金を支払わなくてはならず、労働の値段が徴兵制より相対的に上がる。しかし徴兵制は、適性のない人を軍隊に入れて向かない作業に従事させることになるので、予算費用は低くても機会費用は高くなってしまう。総志願制の軍隊の政府は、労働の値段が高いので、より資本集約的な軍隊をめざす、と分析されています。
本書には、訳者による「事業・プロジェクトとしての戦争」という論文が付録として収録されています。確かに、戦争を事業として見てみると、という観点は本書には抜けているので、良い付録となっています。この中で、日清戦争と自衛隊のイラク派遣とが、実例として取り上げられ、「事業の収益性」という観点から分析されています。
せっかくの分析ですが、日清戦争について、戦争費用(支出):2335億円、賠償金(収入):3682億円とされ、3ケタ間違ってしまっている(実際は2.3億円と3.6億円)ところが、ちょっと残念です。また割引率と現在価値を使って事業の採算性を評価することは、企業の中で新規事業計画や他企業の買収を立案評価する業務に関わっている人にはおなじみの手法ですが、そうした業務経験のない方には理解が少々難しいと思いますので、とくに割引率はどういう考え方で設定されるかについて、もう少し解説があると良かったのではないか、またこの論文には注記が一切なく、参考図書などが挙げられていると、もっと分かりやすくなって良かったのではないか、という気がしています。
本書は、本ウェブサイト中、「7 日清戦争の結果 - 7c 日清戦後の軍拡」のページで、引用等を行っています。
ニミッツ ポッター 共著 実松譲 冨永謙吾 共訳 『ニミッツの太平洋海戦史』
恒文社 1962
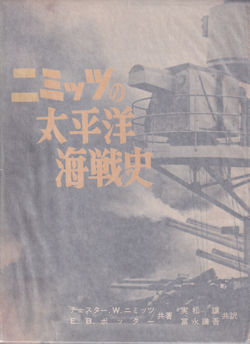
原著は、Edited by E. B. Potter and Fleet Admiral Chester Nimitz, USN, "The Great Sea War" 1960。
原著は、第二次世界大戦の海戦全体、すなわち、ヨーロッパ戦線の大西洋・地中海および太平洋戦争全体についての海戦史なのですが、訳書は、そのうち太平洋戦争関係だけを取り出したものです。
また、訳書には「ニミッツ ポッター 共著」とありますが、原著では「ニミッツ ポッター 編集」となっています。原著を確認すると、著者名としてポッター自身を含む9人の名前が上げられています。この9人が分担執筆を行ったものを、ポッターが編集、ニミッツも監修した、ということであったようです。
原著の序文には、ハルゼーやスプルーアンスを含む10名以上の海軍将官が、各自が関わった海戦についての原稿チェックや助言を行った、と記されています。ですから、公刊戦史ではないものの、それに準じるようなレベルの内容になっていると理解できます。
訳書では、タイトルに「ニミッツの」と付けられ、「編集」が「共著」に格上げになって、太平洋戦争中に米太平洋艦隊司令長官兼太平洋戦域最高司令官であったチェスター・ニミッツ海軍元帥が全面に押し出されていますが、これは出版社の日本国内における販売策によるものだと思われます。
本書では、事実に即した記述が心がけられており、米海軍にとって、メンツ上は都合が悪い内容であっても、隠さずに記されています。ですから、逆に米海軍が各海戦を通じて、どういう課題が生じ、それぞれにどのようなカイゼンを行ったのか、カイゼンは迅速になされたのかそうではなかったのか、といったこともよく分かるようになっています。
メンツにこだわった日本の戦史と事実に即した本書との間に見られる、そもそもの姿勢の差が、日米両軍で成し遂げられたカイゼン量の蓄積の差となり、最終的な連合国軍の勝利・日本軍の大敗北につながった、と言えるように思われます。
本書については、「4 日清戦争の経過 - 4e 戦闘の総括 戦費と戦死者」のページで言及しています。
なお、本書は大著であるだけに、訳書には誤訳箇所が少なくないように思われます。本書を読まれる場合、原著も手元に置いて、おや、と思う翻訳箇所が出てきたら原著で確認することをお勧めします。
このウェブ・サイトでは、日清戦争当時の日本軍の戦略を、日本史上でかつて実行され成功した戦略、具体的には豊臣秀吉のそれと比較する、また、日清戦争当時にあった朝鮮での強い反日意識の原因となった秀吉の朝鮮侵攻について、具体的に何が行われたのかという確認する、という作業も行いました。次は、秀吉の天下統一戦争および朝鮮侵攻に関する参考図書です。