8c 日清戦争の研究・資料(海外)
日清戦争についての研究で、本ウェブサイトで参照・参考にしたもののうち、海外研究者による研究書、および、海外著者による同時代資料についてです。
海外研究者による研究書は、日本人研究者とは異なる視点から研究されており、その点で読む価値が大いにあると思います。
このページの内容
① 米人研究者による研究書
● S. C. M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1895(サラー・ペイン 『1894-1895の日清戦争』)
② 中国人研究者による研究書
③ 西洋人の著者による同時代資料
① 米人研究者による研究書
S. C. M. Paine, The Sino-Japanese War of 1894-1895, Perceptions, Power and Primacy
Cambridge University Press 2003
(サラー・ペイン 『1894-1895の日清戦争 - 認識・力・第一位』)
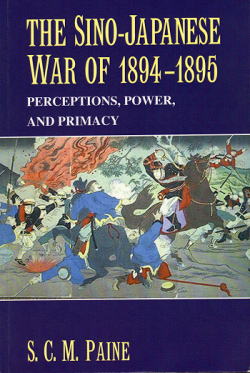
本書の著者は、米国海軍大学(U. S. Naval War College、ロードアイランド州ニューポート)のStrategy & Policyの教授です。女性で海軍大学の教授、というのは、さすがアメリカ、という気もします。同大学のウェブサイトに著者Sarah C. Paineを紹介するページがあります。
海軍大学の教授による著作ではありますが、本書の関心の中心は、日清戦争を構成した個々の戦闘に焦点をあてる戦史研究にはありません。(本書中には、日清戦争での海軍の使い方について、さすがは海軍大学教授、というコメントもありますが。)
日清戦争の前後で、西洋、すなわち欧米列強の日本や中国に対する認識、あるいは日本や中国の自国に対する認識がどう変化したのか、また、その認識の変化は、国際政治にどのような影響を与えたのか、という点に最大の関心が向かっています。
本書は、日本語の翻訳が出ていないので、少し詳しくご紹介します。
本書(サラー・ペイン 『1894-1895の日清戦争』)の狙い
本書のいわば序章である第1章の中で、著者は、本書の狙いを次のように説明しています。要約です。
本書の基本認識 -世界史の新展開の基となった日清戦争
1894-5年の日清戦争は、世界史の新展開の基となる出来事(a seminal event)だったが、西洋の文献ではほとんど無視されてきた。東洋ではそうでなく、この戦争以来一貫して、中国の外交政策の焦点はその結果をやり直すこと、日本の外交政策の焦点はその結果を確認することにあり続けた。
この戦争は、東洋・西洋両方での認識を変えた。中国の弱さの認識は、列強による中国へのはるかに攻撃的な侵入に、日本の力の認識は、日本を帝国主義勢力の中に含めることにつながった。
この戦争は中国にとって転回点であり、中国の絶対不可侵の優位性という頑強な意識基盤を打ち砕いた。極東の勢力バランス、引き続く地域の不安定さ、政治のグローバル化、日清戦争は世界史上の新展開の基となる出来事であった。
本書の目的-日本と中国への西洋の理解の方向転換は、いかにして起こったか
21世紀となる今、西洋で当たり前の見方は、日本は最も工業化した国に区分され、その市民は高い生活水準にあり、この達成のゆえに最高度の尊敬に適合した国である、というもの。この見方に向かっての西洋の認識の変化は、1894-5の日清戦争の結果起こった。対照的に、中国は、その敗北の結果から未だ回復しきっていない。
これから叙述することは、西洋の理解のこの基本的な方向転換がいかに起り、その結末はどうなったかの物語。外交、軍事作戦、国際的な勢力バランスに関する世論へのインパクトに焦点をあてている。
荒っぽすぎるかもしれませんが、本書の焦点について、一言で言ってしまえば、「西洋世界からみた日清戦争とその影響」として要約できるかと思います。
「この戦争以来一貫して、中国の外交政策の焦点はその結果をやり直すこと、日本の外交政策の焦点はその結果を確認することにあり続けた」というのは、現在の日中関係を考える上でも、非常に有用な指摘であるように思われます。(2010年代以降、習近平がトップとなってからの中国は、とくにその傾向を強めているように感じられます。)
著者がそう見ていることの理由の一つに、日清戦争を指す英語のことば、ということがあるように思います。本書の書名で示されているように、日本では、明治期の「日清戦争」と昭和前期の「日中戦争」に異なる名前が付けられていますが、英語では、どちらも"Sino-Japanese War" (日中戦争)なのです。
英語の場合、日清戦争は、前に "the First" が付くか、後ろに "of 1894-95"が付くかして、昭和前期の日中戦争と区別されているだけです。基本はどちらも「日中戦争」なので、現在の中国は「日清戦争=最初の日中戦争」の前の状況に回復させようとしている、という観察にたどり着きやすいのかもしれません。
また、日本は、「最も工業化した国のひとつであり高い生活水準を達成しているので、最高度の尊敬に適合した国のひとつである」こと、すなわち工業化の進展度や生活水準が、国とその国民を評価する場合の欧米流の普遍的な重要基準であることが指摘されています。言い換えれば、現在の日中双方の一部の論者の主張にみられるような、その国の何らかの歴史的独自性に特にこだわり(=メンツ)をもつことは、他国から尊敬を勝ち得る普遍的で重要な基準では全くないことを、あらためて気づかせてくれるようにも思います。
(なお、本ウェブサイト中での、筆者による本書の訳文で、"China"は、それが明らかに日清戦争当時の中国だけを示している場合は、すべて「清国」と訳しています。日本では、「清国」という中国の特定の時期の王朝と、現代の中国あるいは歴史を通貫していう場合の中国とを、区別するのが一般的であると考えたためです。)
本書の構成
本書は下記の構成となっています。
Part I: Clash of Two Orders: The Far East on the Eve of the War
(第1部 二つの秩序の衝突 - 戦争前夜の極東)
1. The Reversal in the Far Eastern Balance of Power
(第1章 極東の勢力均衡の逆転)
2. The Decline of the Old Order in China and Korea
(第2章 清国と朝鮮での旧秩序の衰退)
3. The Rise of a New Order in Russia and Japan
(第3章 ロシアと日本での新秩序の興隆)
Part II: The War: The Dividing Line Between Two Eras
(第2部 戦争 - 二つの時代の区分線)
4. The Beginning of the End: The Outbreak of Hostilities
(第4章 終わりの始まり-戦闘の勃発)
5. Japan Triumphant: The Battles of P’yongyang and the Yalu
(第5章 勝ち誇る日本-平壌の戦いと黄海海戦)
6. China in Disgrace: The Battle of Port Arthur and Weihaiwei
(第6章 清国の不面目-旅順口と威海衛の戦い)
Part III: The Settlement: The Modern Era in Far Eastern Diplomacy
(第3部 決着: 極東外交の近代)
7. The Treaty of Shimonoseki and the Triple Intervention
(第7章 下関条約と三国干渉)
8. The Era of Global Politics
(第8章 国際政治の時代)
9. The Cultural Dimensions of the Sino-Japanese War
(第9章 日清戦争の文化的特質)
Epilogue: Perceptions, Power, and War
(エピローグ: 認識、力と戦争)
本書の特色 ① 日清朝だけでなく、ロシアも加えた4国が対象
本書には、日本での通例の日清戦争研究とは異なる大きな特色が、三つある、と思います。その第一は、本書は、日清朝の3ヵ国だけに焦点をあてているのではなく、ロシアも含めた4ヵ国を対象としていることです。
とりわけ、日清戦争以前のロシアの状況の分析は、三国干渉が発生する伏線として、興味深いものです。著者は、ロシアは通常19世紀の西欧列強と同列に分類されているが、それは間違いである、として、以下のように指摘しています。要約です。
19世紀末ロシアの基本的性格
19世紀末、ロシアは、商業的海洋帝国となっていた西欧列強とは基本的に異なり、中国・トルコとともに、最後まで残った伝統的な大陸帝国であり、その主要な目標は、商業的ではなく領土的な拡張だった。帝国を維持することが、専制支配の継続に重要な、不可欠な正統性を与えるシンボルとなった。
ロシアの産業革命
ロシアの産業革命への反応は、西欧諸国の反応とは基本的に異なっていた。産業革命がイギリスで進行していくにつれ、ロシアの工業化の膨大な努力にかかわらず、イギリスとの生活水準の格差は拡大していった。ロシア政府の工業化計画は、一般的な生活水準の引上げのためではなく、帝国維持のための近代的軍事力の創造という伝統的軍事的な目的で、国家により方向づけられ国家によりコントロールされていた。西欧的な自由市場システムの逆で、ロシアのビジネス活動は、非常に規制されていて、しばしば政府が認めた独占者によってのみ可能であった。
ロシア皇帝アレクサンドル2世は、社会の低層の改革にあえて手を出したが、上層には干渉しようとしなかった。彼の継承者たちは、何もしなかった。その結果ロシアには、中国や朝鮮と同様、社会秩序の崩壊が生じた。中国や朝鮮の同時代人と同じく、ロシア人は西欧や米国の新規の品物には照準を合わせたが、その基底にある文化的礎石は遠ざけた。ロシア・中国・朝鮮はみな、現代化の果実、工業技術が生み出す力は欲しがったが、それが育つ庭は欲しがらなかった。
ロシアの大国意識と対外進出
ロシアの民族主義の発展は、多くのロシア人が抱いてきた大国意識と結びついた。このことは、ロシア政府がバルカンに介入する圧力となった。他の列強との利益競合等のため、バルカンにうまく介入することが困難化、その代りに、帝国の武勇の根拠の証明を求めて、ロシアは目を東方に転じた。極東とペルシャだけが、ロシアが強国の役割を果たせる残された地域だった。
1880年代に、シベリア横断鉄道の予備調査が実施され、建設は1891年に始まった。ロシアの政治家たちは、彼らの栄光の東アジア事業の終着駅にふさわしい朝鮮または中国の港のアイデアとたわむれていた。
日清韓3国と国境を接する唯一の欧州の大国のロシアが、商工業の発展による生活水準の向上に価値を置く西欧流の大国ではなく、領土拡張を重要視する伝統的な大陸帝国であったことは、日清朝3国にとっては、ロシアを近代国家建設でみならうべきモデルとはできず、それどころかロシアが自国の安全保障上の現実の脅威となったという点で、不幸なことであったように思われます。
本書の特色 ② 当時の海外新聞報道を大きく活用
第二の特色は、特に戦争の経過の確認にあたって、清国・日本の現地発行の英字紙(とりわけ、横浜発行のThe Japan Weekly Mail、上海発行のThe North China Herald and Supreme Court and Consular Gazette、天津発行のThe Peking and Tiensin Times)や、欧米で発行された西洋人による当時の新聞報道を広く取り入れていることです。
「広く伝わった見解はその正確性の如何にかかわらずきわめて大きな影響力を持ちえた」と言うのがその理由です。本書の副題で、Perception(認識)という言葉が使われている根元でもあります。
西洋人による新聞報道史料の取り込みは、とりわけ、戦争の実情と清国政府による公式発表との落差の大きさや、西洋の視点から見た清国軍の問題点などを浮かび上がらせる効果があったように思われます。
この点については、このウェブサイトの本文でも、本書からの要約の引用を多数行いました。
本書の特色 ③ 日清両国の意思決定上でのメンツ意識の強さの指摘
第三の特色は、とりわけ清国の(一部には日本の)当局者の判断・意思決定のさいに背景となった、東洋の文化的特質、要するにメンツ意識の影響の強さの指摘であり、これに関する具体的な事例が多数挙げられています。西洋の視点から観察した結果明確化した事柄であるようにも思われます。
著者が指摘しているメンツ意識の例の一部を、要約して挙げておきます。
光緒帝と主戦派
光緒帝はすぐに、清国の軍事力は日本をひざまずかせるのに何も支障はないとの信条をもつ主戦派の影響下に入った。清国の軍事力は無礼な小人を徹底的に打ち負かすだろう。こうした考えは、戦争期間中、漢族の知識階級の思考を支配した。
清国側の開戦詔勅
清国側の開戦詔勅。またも「メンツ」が問題だった。開戦詔勅は、くりかえし、日本人を「倭人」、つまり小人を意味する日本人に対する古代的なきわめて軽蔑的な言葉で、言及した。誰もこの点を見落とすことがないよう、文書を英訳した清国人側は、この言葉が「侮辱的な意味で」使われていることを説明する注記まで行った。
清国からの第1回の正式講和使節の人選
清国は、できるかぎりの長きにわたり、あたかも日本が戦争に負け、相変わらず清国より劣位にあるかのごとくふるまい続けようとした。日本側はこのゲームを完全に理解していて、それに加わろうとは全くしなかった。清国側は、「小人」を同等者として扱うのを拒否することに執着、またその存在が日本側の眼には大きな侮辱となるような者を選ぶやりかたをした。それが清国政府の日本側に対し全くの嘲りを表現するやり方だった。〔清国の使節選任の不適切や、信任状の不備については、当時清国発行の英字紙にも指摘あり〕
日本側は、この〔信任状〕問題で戦って勝利した。しかし、教訓は、清国人の心理の深く埋め込まれた思考にはまだ浸み込んでいかなかった。その一つは、「小人」は劣等であり、清国の生徒であって、いかなる環境にあっても清国の先生にはなれない、というものだった。
講和談判の場所の決定
小さな「メンツ」を埋め合わせるために、清国側は交渉を清国内の旅順か天津で行おうとした。このことは、日本が、請願のために清国に来る嘆願者という見せかけを作るだろう。日本側は拒否した。
下関講和談判での日本側の狙い
日本側の戦争の重要なゴールは、清国に屈辱を与えることだった。戦略的には必須ではない奉天府が主要な領土要求の一部となった。それが清朝の先祖の首府であり初期の清皇帝の墓所の場所である奉天を含む地区であったから。日本側は、何世代もの侮辱への報復として清国の損害を最大化しようとしていた。一方清国側は、支配王朝が権力の座にあり続けられるのに充分な「メンツ」を救おうとしていた。
最後に日本側は、外国貿易に開く都市と川から北京を削除し数も削減し、とりわけ奉天を占領するという要求を取り下げて、清国側にいくらかの「メンツ」を与えた。日本側はまた、賠償金の金額も、満州での領土要求も、免税要求も削減した。
カイゼン視点から申上げれば、メンツにこだわることが、いかに事実の正確な把握を妨げ、また合理的な解決策を見出す上での障害になるか、の実例集であるとも言えます。
日清戦争では「無礼な小人」と軽蔑されても、事実の的確な把握と合理的な判断に努めた日本でしたが、清国側のこの失敗を教訓化しなかったためか、昭和前期には逆に「暴支膺懲」などと称して、メンツ意識をむき出しにしてしまいました。結果はやはり大失敗でした。
ところで、現在の日中間あるいは日韓間の論争も、その少なからざる部分は、具体的な課題に対する現実的な解決策の模索という方向には進まず、双方のメンツ争いに陥ってしまっている、という気がします。お互いがメンツで踏ん張れば、お互いが、事実の的確な把握や、合理的な解決策の提案に踏み出すことはなく、双方が妥協できる合意に至ることは困難になり、論争が永遠に続くでしょう。
近代国家をほぼ作り上げた日清戦争期の日本が、領土割譲要求については急に戦国時代の発想に戻ってしまったのと同様、現在の日本も、日中間や日韓間の論争については日清戦争時代に戻ってしまっている、と言えるのかもしれません。
戦争の結果としての認識の変化
本書の結論として、戦争の結果から生じた主要な変化は、西洋の清国と日本についての認識および清国・日本の彼ら自身についての認識で生起した、として、下記のように述べられています。
西洋の清国に対する認識
清国の状況は末期的で、清国政府は改革を行うことができないため、それぞれの西洋列強は、その独自の利害を守り他国の機先を制するため、独自の行動をとろうとした。
清国人の中国文明に対する認識
1000年以上の間、中国の儒教の伝統とそのアジア世界を共有してきた、中華世界のかつてのメンバーの日本が、西洋のようになるために文明を捨てたのは、前例がないこと。清国人は、文明はひとつしかないものではなく、複数あることを認めるようになった。日本の勝利は、華夷秩序と競合する文明の存在を力に示した。2年しないうちに、皇帝自身が1898年の改革運動の中心に立っていた。
西洋の日本に対する認識
西洋の日本に対する認識も180度転換。西洋の列強は突然、日本は彼らの中の1国であると見なした。日本は戦後の清国の分割に参加する。
この戦争の以前、西洋の考えには、非キリスト教国が近代化することは可能か大きな疑問があった。これ以降、そういう疑問はなくなった。悲しいことに、日本に進行していた変化を部外者が評価するのには戦争が必要だった。
日本人はこの戦争から重要な教訓を引き出した。すなわち、列強は、善悪の道徳的問題や、儒教倫理の伝統的な関心にはあまり関心を払わず、軍事的能力によってのみ、日本はその国益を守ることができる、ということである。
日本人の日本に対する認識
戦争は、明治改革を正当化した。明治政府が二つの重要分野、条約改正と軍事的勝利、をやり遂げ、その両者で日本を国際的に認められた強国としたから。戦争は日本人を共通の目的と共有した熱狂的愛国主義に統合し、勝利はその政治体制に正当性を与えた。
日本の清国に対する認識
戦争は、日本人の他者にたいする認識も変えた。それは1000年の調和的な日中関係の土台を、永久に弱らせた。
本書のほんの一部だけを紹介申し上げました。本書は、翻訳される価値が十分にある一書ではないか、と思います。本書は、日本のアマゾンから注文・取り寄せができます。
本ウェブサイトでは、以下のページで、本書から引用等を行っています。
② 中国人研究者による研究書
中国人研究者による研究書には、下記があります。
戴逸・楊東梁・華立 共著 (華立監訳、岩田誠一・高美蘭 共訳)
『日清戦争と東アジアの政治』
大阪経済法科大学出版部 2003
本書は、日清戦争開戦100年の年に中国で刊行された、『甲午戦争与東亜政治』(中国社会科学出版社 1994)の邦訳です。日清戦争の前史に関しては1860年代から始めて、日清戦争後日露戦争に至るまでの時期が扱われています。
本書の最大の特徴は、日清戦争についての、中国側からの視点による研究書である、という点にあります。そのため、当然ながら中国国内の史料が豊富に活用されており、開戦直前から講和の前後まで、清国側は列強からの調停にどれだけ頼ろうとしていたか、その間の清国政府内の論争はどのようなものであったか、日清戦争が清国に与えた影響はどのようなものであったのか、などについての記述が、日本の研究書と比べ非常に豊かです。
とりわけ、清国政府内での主戦派対講和派の激しい対立の具体的な状況については、日本の研究書にはない詳しさで記述されています。現実に、遼東半島から威海衛まで次々に陥落して、軍事的には完全に連戦連敗であるにかかわらず、清朝政府内で大きな勢力をもつ主戦派は、その現実を客観的に判断することが全くできなかったようです。
清国の主戦派は、戦争遂行の力量も、効果的な防衛反攻策や列強からの支援獲得の思案もないのに、講和には反対していた状況は、日清戦争での清国の戦争遂行力と講和交渉力の程度を象徴するものであった、という気がします。
日清戦争の全体像を理解する上で、本書も、読む価値がある研究書の一冊であるように思います。
本書からは、本ウェブサイト中の「7 日清戦争の結果 - 7a 東アジアの不安定化」のページで引用等を行っています。
③ 西洋人の著者による同時代資料
以下は、日清戦争の前後の時期に、日清朝3国に旅行した、あるいは満州に居住した西洋人が書き残した記録についてです。
イザベラ・バード (時岡敬子 訳) 『朝鮮紀行-英国婦人の見た李朝末期』
講談社学術文庫 1998

本書の原著は、Isabella Bird Bishop, Korea and Her Neighbours - A Narrative of Travel, with an Account of the Vicissitudes and Position of the Country 1898です。原著は、海外の図書館によって、インターネット上で公開されています。
イギリス人で、世界各地を旅行した著者は、早くも1878(明治11)年には日本に来て旅行記を書いています。そして、1894~97年という日清戦争の前後の時期に、朝鮮を4度訪れ、朝鮮国内でまだ外国人があまり立ち入ったことがなかった地域へも旅行しています。その時の旅行記が本書です。
著者は、実際に見聞したことについて、大変に的確な観察眼を持っていた女性であると思います。それだけでなく、政治・経済などについても、イギリスをはじめとする欧米外交官や、その土地で暮らしている欧米人などから聴取して、かなり正確な状況理解をしていたようです。
当時の朝鮮の状況の具体的なイメージをつかむのには、本書がなにより優れていると思います。また旅行中、仁川では朝鮮に出兵してきた日本兵を、そこから一時退避して出かけた満州では朝鮮に出征する清国兵を目撃しています。また、当時の日本の対朝鮮政策に対するコメントも含まれています。
そうした点から、日清戦争の研究者にとっても必読書の1冊であるように思います。
本書からは、本ウェブサイト中の下記のページで、引用等を行っています。
クリスティ (矢内原忠雄 訳) 『奉天三十年』 上下2冊
岩波新書 1938
原著は、 Thirty Years in Moukden 1883 - 1913, Being the Experiences and Recollections of Dugald Christie, C. M. G., edited by his Wife, 1914です。これも、原著は、海外の図書館によって、インターネット上で公開されています。
矢内原忠雄の邦訳は、岩波新書の赤版第1号です。現在は新本では出ていませんが、古書が簡単に手に入ります。
キリスト教の伝道医師として1883年に満州・奉天に来たスコットランド人、デュガルド・クリスティによる奉天での生活の記録です。クリスティは、日清戦争前の奉天では、平壌の戦いで戦死した左宝貴将軍と親交がありました。また開戦後、日本軍が満州に軍を進めると、クリスティは営口に避難しましたが、そこを日本軍が占領したため、日本による占領地行政も経験しました。これに関する記述は、上巻にあります。
本書からは、本ウェブサイト中、「4 日清戦争の経過 - 4b7 中盤戦⑦ 遼河平原と占領地」のページで、引用等を行っています。
F. A. マッケンジー (渡部学 訳注) 『朝鮮の悲劇』
平凡社東洋文庫 1972
原著は、Frederick Arthur McKenzie, The Tragedy of Korea 1908。
本書も、日清戦争期の朝鮮についての記述を含んでいます。しかし、ジャーナリストであったマッケンジーが実際に朝鮮に来たのは1904年以降であり、日清戦争期についての記述は、著者自身の直接の見聞に基づくものではありません。しかも日清戦争期についてマッケンジーが使っている資料は、事実をどこまで的確に伝えているかについて、疑問が湧くものも混じっています。
すなわち、著者自身が見聞している日露戦争期については確かに資料の一つと言えますが、日清戦争期については、資料としてはあまり使えないように思われます。この点、ご参考まで。
次は、日清戦争の公刊戦史や写真集についてです。